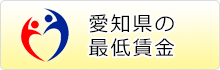⑫ 万葉遺跡 山下橋
 『旅にして物恋しきに山下の 赤のそほ船沖へ漕ぐ見ゆ』
『旅にして物恋しきに山下の 赤のそほ船沖へ漕ぐ見ゆ』
この歌は大宝2年(702)持統上皇が三河に御幸されたとき、供奉した高市連黒人の作です。その大意は「都をあとにしてはるばると遠い国へやって来たが、次第に故郷が恋しくなってきた。そんな気持ちで山の上から海を眺めると、山の下のなぎさから朱塗りの船が沖へ向って漕いで行くのが目に入った。この船はまさしく都の方へ向っていると思ったとき、郷愁を押え切れなかった」ということでありましょう。
歌詞のうち「山下」の2字が論議の的とされており、宝飯地方史資料の1冊『三河文献集成』もこの点にふれていますが、単に山の下という普通名詞であろうという説、固有名詞であるとする説、大恩寺山をさすのであろうという説等々があります。その中で、沖へ進む船を山の下に見ることができる状況に、最もふさわしいのは大恩寺山であろうと思われます。昔は御津神社近くまで舟が着いたとの伝承もあり、当時の大恩寺山の南麓は、海が近くにまで迫っていたものと思われます。
愛知大学教授であった津之地先生もこの説を採り、山麓の青葉がくれに紺碧の海を丹塗りの船が進むという、色彩のコントラストが美しいと指摘されています。
みと歴史散歩:❶駅中心に 平成12年2月発行より